建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた要件を全て満たす必要があります。
特に知事一般許可の場合、主な要件とそれに関連する必要なものについて、以下の7つの観点から詳しくご説明します。
ご自身での検討が難しい場合は、コペル行政書士事務所までお問い合わせください。

※このページに登場する書式は長崎県のホームページよりご確認いただけます。
1. 常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)
建設業の経営業務を適切に管理する能力を有していることが求められます。これは、建設業法第7条第1号で「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と規定されています。
定義
「常勤役員等」とは、法人においては業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者、個人事業主の場合には本人または支配人を指します。ここでいう「これらに準ずる者」には、取締役会の決議を経て、建設業の営業務の執行に関し、業務執行権限の委譲を受け、その業務執行に専念する執行役員等が含まれます。
経験
常勤役員等のうち1人が、以下のいずれかの経験を有している必要があります。
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験。
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位(例:支店長、営業所長等で、営業取引上対外的に責任を有する地位)での経験。
- 建設業に関し、6年以上の経営業務を補佐した経験(資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務全般に関する経験を指します)。
→この補佐経験は、経営業務の管理責任者に準ずる地位(役員等に次ぐ職制上の地位)での経験を指し、経営業務の管理責任者としての経験や執行役員等としての経験と通算して6年以上でも認められます。
専任技術者との兼任に関しては同一の営業所(原則として本社または本店等)内に限って、常勤役員等が専任技術者を兼ねることは可能です。
必要書類例
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)
- 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第7号の2別紙一及び別紙二)
- 商業登記簿謄本、閉鎖登記簿謄本(法人の場合)
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しなど、常勤性を確認できる資料
- 個人事業主の場合は、受付印のある「個人事業開業届出書」(県税事務所提出用)の控え、給与台帳、出勤簿など
- 執行役員等の場合は、組織図、業務分掌規程、取締役会の議事録、人事発令書など、その地位や権限、経験期間を証明する書類
注意事項
- 自己証明は、証明者(原則として使用者)からの証明が得られない正当な理由がある場合に限り認められます。喧嘩別れで聞きづらいなどは正当な理由に該当しません。
- 無報酬の役員については、その理由と常勤状況について個別に調査が行われる場合があります。
- 略歴書や証明書に虚偽の記載があった場合、虚偽申請として許可が拒否または取り消される可能性があります。
「常勤役員等」に関してはすでにコラムで詳しく解説していますので、もっと深く知りたい方はぜひご参照ください。


2. 営業所技術者(旧:専任技術者)
建設工事の請負契約の締結および履行において、技術上の管理を行うために、営業所ごとに専任の技術者を配置する必要があります。これは建設業法第7条第2号で「その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任の者として置く者であること」と規定されています。
定義
営業所技術者(専任技術者)とは、営業所に常勤し、その営業所が請け負う建設工事の契約締結や履行について、技術的な管理を行う者を指します。
専任の意味
原則として、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事することを要し、以下のいずれかに該当する者は専任技術者と認められません。
- 住所またはテレワークを行う場所の所在地が営業所から著しく遠距離にあり、常識的に通勤不可能な者。
- 他の営業所(他の建設業者を含む)の専任技術者となっている者。
- 他の法令により特定の事務所で専任を要する者(例:建築士事務所の管理建築士、専任の宅地建物取引主任者等。ただし、建設業で専任を要する営業所と、他の法令で専任を要する事務所が同一企業、同一場所である場合を除く)。
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任であると認められる者。
技術者の資格要件(一般建設業の場合)
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 指定学科卒業+実務経験
・高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校卒業後、許可を受けようとする建設業に関する建設工事において5年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科(許可を受けたい建設業の種類に応じて土木工学、建築学、電気工学、機械工学など)を修めた者。
・大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業(専門職大学の前期課程修了を含む)後、許可を受けようとする建設業に関する建設工事において3年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者。 - 実務経験のみ
許可を受けようとする建設業に関する建設工事において10年以上の実務の経験を有する者。 - 国土交通大臣の認定
上記1または2に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると国土交通大臣が認定した者。
「実務の経験」の意味
建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指します。単なる雑務の経験は含まれませんが、建設工事の発注において設計技術者として設計に従事したり、現場監督として工事の技術指導監督を行ったりする経験も含まれます。
登録計装基幹技能者講習修了者
次の業種場合のみの営業所技術者要件を満たします。
- 電気工事業
- 管工事業
- 機械器具設置工事業
- 電気通信工事業
上記4業種については「10年以上の実務経験を有し、登録計装基幹技能者講習を修了した者は、一般建設業の営業所に置く専任の技術者と認められる」とされています。(提出書類の簡素化が可能)
監理技術者資格者証による証明
監理技術者資格者証を持っている場合、学校の卒業証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、技術検定の合格証明書などの提出は不要となる場合があります。有効期限が切れていても、資格や実務経験は認められます。(提出書類の簡素化が可能)
技術検定合格通知書による代替
合格証明書の受領までの間は、試験実施機関が発行する「合格通知書」で代替できますが、後日合格証明書での確認が原則となります。
必要な書類例
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)(実務経験で資格を証明する場合)
- 記載する工事内容が具体的なものに限られます
- 実務経験を証明する際には、工事の契約書、注文書、工事発注証明書など、具体的な工事内容を確認できる資料が必要です(証明期間1件/1年が目安)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)(特定建設業許可の要件ですが、一般建設業許可申請で提出を求められる場合もあります)
- 卒業証明書(原本)または卒業証書(写しと原本提示)(指定学科卒業の場合)
- 技術検定合格証明書、各種免許証(建築士、電気工事士など)(国家資格の場合)
- 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険事業所別被保険者台帳照会、所得税確定申告書など、常勤性を確認できる資料
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習の修了証など
「営業所技術者」に関してはすでにコラムで詳しく解説していますので、もっと深く知りたい方はぜひご参照ください。

初めて建設業許可を取る際に資料になる、「軽微な工事」時代の契約書や請書に関して詳しく解説しています。
会社の未来のために、許可取得を意識した瞬間から整えるようにしましょう。


3. 社会保険加入
適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが建設業許可の要件として求められています。
加入義務
健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に基づく適用事業所として、社会保険への加入が義務付けられています。
- 『営業所』という用語は建設業許可の規定上の呼称ですが、社会保険の加入義務は健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法に基づく事業所単位で判断されます。
- 法人の場合は、事業所の規模を問わず強制適用事業所となるため、本店・支店を含む全ての拠点で加入義務があります。
- 個人事業主の場合は、常時使用する従業員が5名以上の事業所が適用事業所となります。
- 雇用保険は、労働者を1名でも雇用する事業所すべてが適用対象です。
- したがって、建設業許可申請における「営業所ごとの社会保険加入要件」とは、実際に保険法令上の適用事業所となる拠点において3保険に適切加入していることを示します。
- 法人は、強制適用事業所として社会保険加入が義務付けられています。
必要書類例
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 申請時の直前の健康保険および厚生年金保険の保険料納入に係る「領収証書または納入証明書」の写し、またはこれに準ずる資料
- 申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えおよび、これより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し、またはこれに準ずる資料
- これらの書類を提出できない場合は、受付印のある届出書の写しなど、届出を提出していることが確認できる資料
- 社会保険の資格証明の取得に時間がかかる場合は、暫定的に受付印のある「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の控えで確認が可能な場合があります(後日、資格証明書の提出が必要)
- 雇用保険の場合は「被保険者証」などで確認します
4.誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。これは建設業法第7条第3号に定められています。
不正・不誠実な行為の例
- 詐欺・脅迫による契約締結
- 架空請求・不正請求による横領
- 文書偽造(契約書・施工体制台帳等の偽造)
- キックバック(違法な紹介料)や過剰接待による利益供与
- 以下に該当すると、許可要件を満たさないとみなされます。
- 他法令(建築士法、宅地建物取引業法など)で免許取消処分を受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者または暴力団による経営支配を受けている 等
以上に該当しない限り、通常の施工・契約履行であれば「誠実性」の要件は満たされます。
必要書類
- 誓約書(様式第6号):建設業法第8条の欠格要件に該当しないことを誓約する書面です。
- 役員等一覧表
注意事項
- 誓約書は、訂正が認められない書類です。
- 過去に不正または不誠実な行為があったと認められる場合、許可が下りない可能性があります。
5. 財産的基礎または金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。これは建設業法第7条第4号に規定されています。
要件(一般建設業の場合)
- 建設業法第7条第4号および建設業許可事務ガイドラインにより、一般建設業許可の財産的基礎要件として、次のいずれか一つを満たすことが明確に規定されています
①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間建設業許可を受けて継続営業した実績があること。 - 「財産的基礎」は、法人の場合は貸借対照表の純資産の状況、個人の場合は事業主借勘定、事業主貸勘定、利益の状況等から判断されます。
- 「金銭的信用」は、取引金融機関からの信用状況や融資証明などから判断されます。
必要書類例
法人
- 直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表(様式第15号~第17号の3)
- 主要取引金融機関名を記載した書面(様式第20号の3)
個人
- 直前1年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書(様式第18号、第19号)
- 主要取引金融機関名を記載した書面(様式第20号の3)
注意事項
- 新規に事業を開始したばかりで、まだ決算期が到来していない場合は、開業届出書や預金残高証明書などで確認される場合があります。
6. 欠格要件
建設業許可を受けようとする者が、建設業法第8条各号に掲げられている欠格要件のいずれにも該当しないことが求められます。これらの要件に該当する場合、許可は与えられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 建設業許可の取消し処分を受けてから5年を経過しない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などの一定の法令の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(またはその役員等)が上記のいずれかに該当する者。
- 法人で、その役員等または政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
必要な書類例
- 誓約書(様式第6号)
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人など)の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
注意事項
- 誓約書は、申請者本人(法人の場合は代表者)が記名し、訂正は認められません。行政書士が代理申請する場合でも、誓約書の申請者欄には行政書士の記名は不可とされています。
- 欠格要件の確認は厳格に行われます。
7. 営業所の観点
建設業を営むためには、適切な営業所を設ける必要があります。
定義
営業所の定義
建設業法における営業所とは、本店または支店、あるいは政令で定めるこれに準ずるものを指します。
「主たる営業所」とは
建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所を指します。通常は本社、本店等ですが、単なる登記上の本社や本店等で実態を伴わないものは、営業所として認められません。
実態の確認
営業所には、常勤役員等や専任技術者が常勤し、請負契約の締結や見積もり、入札など、建設業の営業行為を行う実態が求められます。単に書類上の事務所では足りません。
事務所の形態
一般的な事務所としての形態を有している必要があります。他の事業者と同居している場合や、バーチャルオフィス、自宅兼事務所の場合は、他の来訪者との混同を避けるための明確な区別(独立した出入り口、名札、看板の掲示など)や、事業活動の実態が確認できることが求められます。
写真での確認
営業所の外観、入口、内部の写真の提出を求められることがあります。
必要な書類例
- 営業所一覧表(建設業許可申請書別紙二(1) または (2))
- 「主たる営業所」は、営業所一覧表に記載された営業所のうち、統轄・指揮監督する権限を持つ一つを指します
- 営業所の写真(外観、入口、内部など)
- 不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写しなど、営業所の使用権限を証明する書類
注意事項
- 名目上の営業所や実態のない営業所は認められません。
- 営業所の所在地、電話番号、郵便番号などの正確な記載が必要です。
その他、許可申請に必要な書類・情報
上記で述べた各要件を満たすために提出する書類の他に、以下のような書類も必要となります。
- 許可申請書(様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号):申請日直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金額を記載します。金額の大きい順に記載し、公共工事と民間工事の区分も示します。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第3号)
- 使用人数を記載した書面(様式第4号)
- 定款(法人の場合):現在の事業目的や資本金、役員構成などが記載されているもの。
- 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面(様式第14号):法人の場合。
- 登記事項証明書:商業登記されている場合。個人の場合、法定代理人が法人である場合にはその法定代理人の登記事項証明書も必要。
- 営業の沿革を記載した書面(様式第20号)
- 建設業者団体に所属する場合の名称及び所属年月日を記載した書面(様式第20号の2)
- 納税証明書:国土交通大臣許可を申請する場合は法人税または所得税、都道府県知事許可を申請する場合は事業税の直前1年の各年度における納付すべき額および納付済額を証する書面。
- 委任状:行政書士が代理で申請を行う場合のみ必要。(電子申請の場合は別途手続きあり)
※このページに登場する書式は長崎県のホームページよりご確認いただけます。
ほかにも許可を取った後に確認をする必要がある項目についても下記のコラムにまとめています。
ぜひご参照ください。

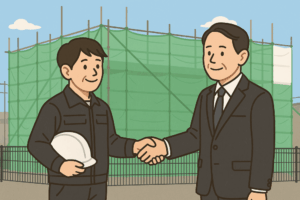
建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、受注拡大の大きな一歩となります。
「自分でやるには不安がある」「どこまで準備が必要か分からない」
そんなときは、建設業許可申請に精通したコペル行政書士事務所にご相談ください。
お電話・LINE・メール、どの方法でも構いません。まずは一度、具体的な状況をお聞かせください。
以下からお気軽にお問い合わせください。

