「ウチの現場、置くのは主任技術者でいいんだっけ?それとも監理技術者?」
「専任ってどういう意味?どの現場でも絶対に一人の技術者を貼り付けなきゃいけないの?」
「最近、金額の要件が変わったって聞いたけど、具体的にどうなったんだ?」
「法律違反で罰則を受けたくないけど、正直、細かいルールまで追いかける時間がない…」
日々、現場と会社経営の最前線で戦う建設業の社長様。このような「技術者配置」に関する悩みは、尽きることがないのではないでしょうか。特に、主任技術者と監理技術者の違いや、「専任」という言葉の本当の意味は、ベテランの社長様でさえ混同しがちな、複雑で厄介な問題です。
法律の条文を読んでも頭に入ってこないし、かといって曖昧な知識のままでは、知らないうちに法令違反を犯し、会社の信用を失いかねません。
この記事は、そんな多忙な社長様のために、工事現場の技術的トップである「主任技術者」と「監理技術者」にテーマを絞り、その役割と配置ルールを、どこよりも丁寧に、そして圧倒的にわかりやすく解説することをお約束します。
「つまり、どういうこと?」「社長として、何をすればいいの?」という疑問に徹底的に寄り添い、明日からの現場運営にすぐに役立つ知識をお届けします。
この記事をぜひ読んでいただきたい方
- 建設工事の現場に、どの技術者を配置すればいいか迷うことがある事業主様
- 「主任技術者」と「監理技術者」の明確な違いを、スッキリ理解したい方
- 「専任」や「兼務」といったルールの最新情報を、正しく把握したい方
- 元請として、下請業者への指導や管理に責任を持つ立場の社長様
- コンプライアンスを徹底し、安心して事業を拡大していきたいと考えている方
この記事を最後まで読めば得られる知識
- どんな工事に「主任技術者」が必要で、どんな工事に「監理技術者」が必要かが、一目でわかるようになります。
- 技術者を「専任」で配置しなければならない具体的な金額や工事の種類が、明確に理解できます。
- 令和7年2月から変わった最新の金額要件を、正確に把握できます。
- 技術者不足に対応するための「兼務」のルールを知り、効率的な人員配置のヒントが得られます。
- 法令違反のリスクを避け、自信を持って現場を運営するための具体的なアクションプランが見えてきます。
時間がない社長様へ!この記事の3行要約
- 全ての工事現場に「主任技術者」は必須。 ただし、元請として大規模な下請工事(5,000万円以上)を発注する場合は、よりハイレベルな「監理技術者」が必要になる。
- 公共性の高い重要な工事で一定金額以上の場合、技術者は「専任」となり、原則その現場に付きっきりになる必要がある。
- 法律は複雑で頻繁に変わるため、「ウチのケースはどうだろう?」と少しでも迷ったら、自己判断せず専門家に相談するのが一番の近道。
「専門家に話を聞いてみたい」と思ったら、今すぐご相談ください。
この記事を読んで、「やっぱりウチのケースは複雑だ」「すぐに専門家の意見を聞きたい」と感じた社長様。その直感を大切にしてください。
建設業の技術者配置に関するお悩みは、ぜひコペル行政書士事務所にご相談ください。複雑な法令を紐解き、貴社の状況に合わせた最適なアドバイスをいたします。
初回のご相談は1時間無料です。まずはお気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。

建設業者様のサービス内容に関しては以下をご覧ください。
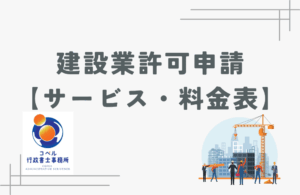
その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

すべての基本!「主任技術者」はなぜ必要か?
まず、建設業の現場における大原則からお話しします。
それは、「建設業許可を受けている会社が施工するすべての工事現場には、必ず『主任技術者』を配置しなければならない」ということです。(建設業法第26条第1項)
これは、元請・下請、工事金額の大小にかかわらず、絶対に守らなければならないルールです。500万円以下の軽微な工事を除き(解釈は分かれるが)、建設業許可業者として工事を行う以上、全ての現場に技術的な責任者が必要なのです。
では、主任技術者の役割とは何でしょうか?
一言で言えば、「その工事現場の品質・安全・工程を守る、技術的な現場監督」です。 具体的には、以下の3つの重要な職務を担います
- 施工計画の作成:工事を始める前に、どのような手順で、どのような工法で進めていくか、詳細な計画を立てます。
- 工程管理:計画通りに工事が進んでいるか、日々の進捗を管理し、遅れが出ないように調整します。
- 品質管理・安全管理:設計図書通りの品質が確保されているか、材料や施工方法をチェックします。また、現場で働く作業員の安全を確保するための対策を講じ、事故を未然に防ぎます。
このように、主任技術者は工事の始めから終わりまで、その現場の技術的なすべてに責任を持つ、極めて重要なポジションです。

主任技術者になれるのはどんな人?
主任技術者になるための条件は、以前解説した「一般営業所技術者」と全く同じです。
以下の3つのルートのいずれかを満たす必要があります。
- ルート①:国家資格を持っている(例:2級建築施工管理技士、第二種電気工事士など)
- ルート②:学歴 + 実務経験がある(例:指定学科の高校卒+5年以上の実務経験)
- ルート③:10年以上の実務経験がある
つまり、営業所に置く技術者(営業所技術者)と、現場に置く技術者(主任技術者)は、求められる資格や経験のレベルが同じ階層にある、とイメージすると分かりやすいでしょう。
また、直接的かつ恒常的な雇用関係が求められ、出向社員や派遣社員は認められません。
「監理技術者」が登場する特別なケースとは?
原則として、すべての現場には主任技術者を置けば良い、と説明しました。
しかし、ある特別な条件が揃ったとき、主任技術者では力不足とされ、よりハイレベルな技術者、「監理技術者」を配置することが義務付けられます。(建設業法第26条第2項)
その特別な条件とは、以下の2つを両方とも満たした場合です。
- あなたの会社が「元請」であること
- その工事で、下請業者へ発注する工事代金の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000円以上)であること
また、主任技術者と同じく、直接的かつ恒常的な雇用関係が求められ、出向社員や派遣社員は認められません。
これが、監理技術者が登場する場面です。
なぜ、この条件のときだけ、主任技術者ではダメなのでしょうか?それは、5,000万円という多額の下請契約を束ねる元請には、個々の工事を管理する能力だけでなく、多数の下請業者をまとめ上げ、指導監督する、より高度で総合的なマネジメント能力が求められるからです。
監理技術者の「監理」という言葉には、単に工事を見る(管理)だけでなく、下請業者を適切に指導し、全体を統括する(監督・指導)という意味合いが強く込められています。
監理技術者の重要な役割
監理技術者の職務は、主任技術者の業務(施工計画、工程管理、品質・安全管理)に加えて、「下請負人の指導監督」という非常に重要な役割が加わります。
- 下請業者の技術レベルを把握し、適切な指導を行う
- 下請業者が提出する施工計画や安全書類をチェックし、承認する
- 複数の下請業者が関わる工事で、作業の調整や連絡役を担う
つまり、監理技術者は、元請の技術責任者であると同時に、下請業者全体のチームリーダーでもあるのです。
監理技術者になれるのは、選ばれしエリート!
監理技術者になるための条件は、主任技術者よりも格段に厳しく、「特定営業所技術者」と同じレベルが求められます。
- 1級の国家資格を持っていること(例:1級土木施工管理技士、一級建築士など)
例外で監理技術者補佐のみでしたら1級技士補でも務められます。
特に、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の「指定建設業」7業種については、下記の例の認められず、1級の国家資格が必須となります。 - (指定建設業の7業種以外)「指導監督的実務経験」があること
- 指定建設業の場合は国土交通大臣の特別認定者でも務めることができます。
また、工事現場においては、監理技術者資格者証の携帯が義務づけられ、 発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
【ポイント整理】
- 主任技術者 → 全ての現場の基本。資格は2級でもOK。
- 監理技術者 → 元請で大規模な下請工事を行う場合のみ登場。原則1級資格が必要。
最大の難関!「専任」のルールを徹底解剖
さて、主任技術者と監理技術者の違いがわかったところで、次なる難関、「専任」のルールについて解説します。
「専任」とは、簡単に言えば「その技術者が、他の現場と掛け持ちせず、その工事現場に付きっきりで従事すること」を意味します。
「えっ、うちの会社は技術者が少ないのに、全部の現場に一人ずつ貼り付けなきゃいけないの!?」と驚かれた社長様、ご安心ください。すべての現場で「専任」が求められるわけではありません。
「専任」が必要になるのは、以下の2つの条件を両方とも満たす、特に重要で規模の大きな工事に限られます。
- 工事の種類:公共性のある施設や、多数の人が利用する施設に関する重要な建設工事であること。(例:国や自治体が発注する公共工事、学校、病院、デパート、共同住宅など)
→一般的に戸建住宅以外はこれに該当すると言われています。 - 工事の金額:請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)であること。

【重要!】令和7年2月1日からの金額改正
この金額要件は、資材費や人件費の高騰を反映し、令和7年2月1日から引き上げられました。
- 改正前:4,000万円(建築一式は8,000万円)
- 改正後:4,500万円(建築一式は9,000万円)
この新しい金額を、しっかりと頭に入れておいてください。
つまり、公共性のある施設と認められない民間工事では、たとえ請負金額が1億円を超えていても、原則として「専任」の義務は発生しないのです。
逆に言えば、公共工事の入札に参加し、4,500万円以上の工事を落札した場合は、必ず専任の技術者を一人、その現場に確保しなければならない、ということになります。
技術者不足の救世主?「兼務」のルールを知って効率化を図る
「専任のルールはわかったけど、やっぱり技術者が足りない…」
「複数の小規模な現場を、一人の技術者に見てもらうことはできないのか?」
そんな社長様のために、法律はいくつかの「兼務(掛け持ち)」を認める例外ルールを設けています。これをうまく活用することが、効率的な会社経営に繋がります。
兼務が認められる主なケース
- 専任が不要な工事間での兼務
専任義務のない工事(公共性のない民間工事や、4,500万円未満の公共工事など)であれば、同一の技術者が複数の現場を掛け持ち(兼務)することが可能です。ただし、それぞれの現場の技術的管理を適切に行えることが大前提となります。 - 特例:近接した場所での専任工事の兼務(監理技術者は原則適用外)
これが、技術者不足に対応するための重要な特例です。
たとえ専任が義務付けられている工事であっても、以下の条件を満たす場合には、同一の技術者が原則2の現場を兼務することが認められています。
・それぞれの工事が、密接な関連があること
・それぞれの工事現場が、近接した場所(工事現場の相互の間隔が10km程度の場合も適用)にあること
・元請負人が同一であること
例えば、同じ団地内で2棟の公共住宅を同時に建設する場合などが、このケースに該当する可能性があります。 - 営業所技術者との兼務
以前は厳しく制限されていましたが、法改正により、一定の条件下で営業所にいる「営業所技術者」が、現場の「主任技術者」や「監理技術者」を兼務できる道も開かれています。
・請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)であること営業所と現場が近接していること営業所と現場が近接していること
・ICT(情報通信技術)を活用した遠隔管理体制が整っていること
・営業所と現場が近接していること
など、いくつかの細かい要件がありますが、うまく活用すれば、人材を最大限に活かすことが可能です。
これらの兼務ルールは非常に複雑で、個別のケースごとに判断が必要です。「この現場とこの現場、兼務できるかな?」と迷ったら、必ず許可行政庁や専門家に確認することをお勧めします。
まとめ:社長が今すぐやるべきことと、未来への備え
ここまで、主任技術者、監理技術者、そして「専任」と「兼務」のルールについて、詳しく解説してきました。最後に、この知識を活かして、社長様が会社を法令違反のリスクから守り、さらに発展させていくための具体的なアクションプランを提案します。
アクションプラン①【リスク管理】現場ごとの「技術者配置チェックリスト」を作成・運用する
まずは、受注した工事ごとに、以下の項目を必ずチェックする習慣をつけましょう。
- 元請か?下請か?
→ 元請の場合、次のステップへ - 下請への発注総額はいくらか?
→ 5,000万円以上か? → YESなら「監理技術者」が必要 - 公共性のある工事か?
→ YESの場合、次のステップへ - 請負代金の総額はいくらか?
→ 4,500万円以上か? → YESなら原則「専任」が必要
この簡単なチェックリストを運用するだけで、「うっかり」による法令違反を劇的に減らすことができます。
アクションプラン②【人材戦略】技術者の「資格取得」を会社として支援する
技術者不足は、今後さらに深刻化していきます。優秀な技術者の確保と育成は、会社の未来を左右する最重要課題です。
- 資格取得支援制度の導入:受験費用や講習費用の補助、資格手当の支給など、社員が資格取得に挑戦しやすい環境を整えましょう。
- キャリアパスの提示:「2級を取ったら、次は1級を目指そう。1級を取れば、監理技術者として大きな現場を任せるし、給与も上げる」といった具体的なキャリアパスを示すことで、社員のモチベーションを引き出します。
会社の成長は、社員の成長と共にあるはずです。社長が率先して、人材育成への投資を行う姿勢を見せることが何よりも大切です。

アクションプラン③【経営判断】迷った時の「相談相手」を確保する
建設業法は、非常に複雑で、毎年のように何かしらの改正が行われます。社長がすべての法改正を完璧に追いかけるのは、現実的ではありません。
そして、最も怖いのは「知らなかった」という言い訳が通用しないことです。法令違反が発覚すれば、指示処分や営業停止といった厳しい罰則が待っています。
だからこそ、経営判断に迷ったとき、法的な解釈に不安を感じたときに、すぐに相談できる専門家の存在が不可欠なのです。
その悩み、ぜひ聞かせてください。あなたの会社の「かかりつけ医」になります。
ここまで記事を読み進めてこられた社長様は、きっとコンプライアンス意識が高く、会社の未来を真剣に考えていらっしゃる方だと思います。
しかし、同時に、
「やっぱり、自分の会社のケースに当てはめると、どう判断していいか分からない…」
「法律の条文を読んでも、結局”通常”とか”密接”とか、曖昧な言葉が多くて不安だ」
「兼務のルールをもっとうまく活用して、経営を効率化したい」
といった、新たな課題や不安を感じているかもしれません。
そのお悩み、コペル行政書士事務所にお聞かせください。
コペル行政書士事務所は、建設業許可の申請やコンプライアンス対応を専門とする行政書士事務所です。貴社の具体的な状況を丁寧にお伺いし、法律の専門家として、そして経営のパートナーとして、最適な解決策をご提案いたします。
「こんな初歩的なことを聞いてもいいのだろうか?」などと、ためらう必要は一切ありません。社長のどんな些細な疑問や不安にも、真摯に向き合います。
初回のご相談は1時間無料です。貴社が抱える問題を整理し、進むべき道を照らすだけでも、大きな価値があるはずだと考えています。
まずはお気軽にお電話、または下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談を心よりお待ちしております。

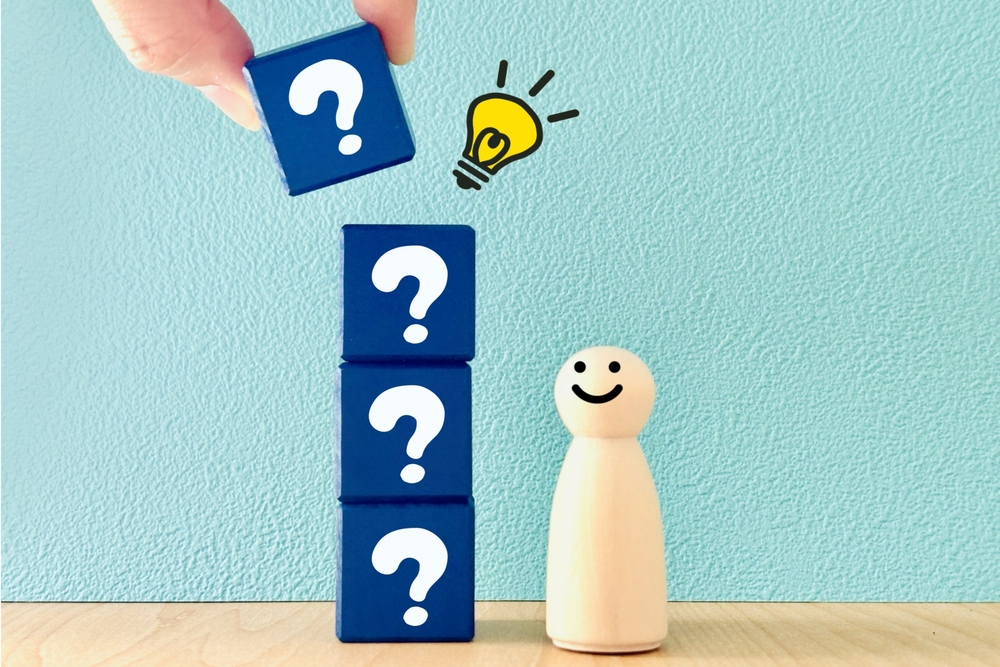
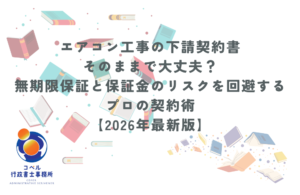
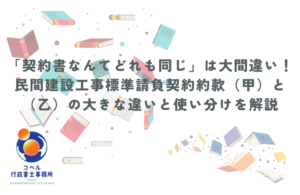
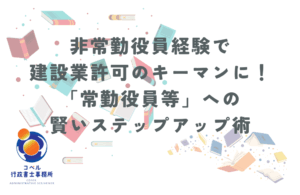





コメント