「大きな契約が取れそうだ!」
「この金額なら、今の許可のままで大丈夫だろう」
「…でも本当に大丈夫かな?」
事業を成長させる中で、請負金額の計算は常に付きまとう重要なテーマです。
しかし、建設業法における金額の数え方には、実は2つの異なるルールがあることをご存じでしょうか?
特に、お客様や元請けが用意した材料費を金額に含めるか、含めないかという違いは、知らなければ許可違反という大きなリスクにつながりかねません。
この記事では、日々多忙な建設業の経営者様に向けて、法律の難しい話は抜きにして、初めて建設業許可が必要になるタイミングの契約金額と特定建設業許可が必要になる場合における金額計算の決定的な違いを、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読んでほしい人
- 一般建設業許可をお持ちで、これから事業を拡大していきたい経営者の方
- 元請として、下請業者に大きな金額の工事を発注する機会がある方
- 「500万円未満」や「5,000万円以上」といった金額の基準を、自己流で判断している方
- お客様支給の材料がある工事を請け負うことが多い一人親方・工務店の方
この記事を読んで得られる知識
- 許可が不要な「軽微な工事」における請負金額の正しい計算方法
- 「特定建設業許可」が必要になる下請契約金額の計算方法
- 両者の間にある材料費の取扱いという決定的な違い
- 知らないと起こりうる、具体的な失敗事例と回避策
- 法令遵守のために、経営者が今すぐ取るべきアクション
最後まで読めない!という方へ【この記事の3行まとめ】
- 軽微な工事(500万円未満=499万円まで)の判断では、お客様支給の材料費も「含めて」計算する。
- 特定建設業許可(下請代金5,000万円以上=5,000万円から)が必要かの判断では、元請けが提供する材料費は「含めずに」計算する。
- このルールの違いを知らないと、意図せず法律違反になったり、大きなチャンスを逃したりする危険がある。
「自分の場合はどうなるんだろう?」
「ちょっと話だけでも聞いてみたい」
少しでも不安に感じた方は、お気軽にご相談ください。
コペル行政書士事務所では、初回1時間のご相談を無料で承っております。
あなたの会社が抱える課題を、一緒に整理させていただきます。
下記の24時間お問い合わせ専用フォームや公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
直接お電話いただいてもかまいません。お気軽にどうぞ!

建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。
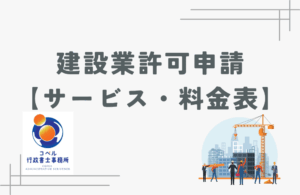
その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

なぜ、金額の数え方が2種類もあるのか?
まず、なぜこんなにややこしいルールになっているのか。
それは、法律がそれぞれの基準で守ろうとしているものが違うからです。
- 軽微な工事の基準(材料費を「含む」)
→目的:小規模な工事でも、実質的な工事規模を正確に把握し、消費者を保護するため。工事全体の価値が大きければ、それ相応の技術力や経営力を持つ許可業者に任せるべき、という考え方です。 - 特定建設業許可の基準(材料費を「含まない」)
→目的:高額な下請契約を結ぶ元請業者の、下請業者に対する支払い能力や指導力を担保するため。「実際に下請けに支払うお金」がいくらかを重視しています。
この目的の違いが、材料費の扱いの違いとなって表れているのです。ちなみに、上記の2ついずれも消費税及び地方消費税を含む金額です。これも念頭に入れて計算していきましょう。
軽微な工事に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

では、具体的な事例で見ていきましょう。

事例で比較!「材料費」でこんなに変わる
ケース1:リフォーム専門 A工務店の悲劇(軽微な工事の場合)
A工務店は、建設業許可を持たずにリフォーム業を営んでいます。
ある日、お得意様からこんな依頼がありました。
「キッチンのリフォームをお願いしたい。工事費は450万円で見積もってほしい。こだわりの海外製システムキッチン(200万円相当)は、私が自分で用意するから」
A社長は「工事費は450万円か。500万円未満だから、許可がなくても問題ないな!」と快諾し、工事を無事に終えました。
うっかりポイント
軽微な工事の金額判断では、お客様が支給した材料の市場価格も、請負代金に合算しなければなりません。
- A工務店の工事費:450万円
- お客様支給のキッチン:200万円
- 法律上の請負金額:650万円
この工事は、実質的に650万円規模の工事であり、建設業許可がなければ請け負えない工事でした。
A社長は、知らず知らずのうちに「無許可営業」という重大な法律違反を犯してしまったのです。
ケース2:元請 B建設の攻防(特定建設業許可の場合)
B建設は、一般建設業許可を持つ中堅ゼネコンです。
ある日、1億円規模の公共工事を受注しました。そのうち、専門的な工事を下請業者C社に発注します。
B建設の担当役員は考えます。
「下請けに出す金額は、工事費4,500万円と材料費2,000万円で合計6,500万円。これは建築一式工事以外だから、5,000万円を超えてしまう。わが社は一般許可しか持っていないから、このままでは契約できない…」
逆転のカラクリ
ここで、特定建設業許可のルールが活きてきます。
特定建設業許可が必要かどうかを判断する下請契約金額には、元請が提供する材料費は含めません。
- 下請契約の工事費:4,500万円
- 元請支給の材料費:2,000万円(計算に含めない)
- 法律上の下請契約金額:4,500万円
合計額は、基準となる5,000万円を下回っています。
したがって、B建設は一般建設業許可のままで、この工事を下請業者C社に発注できるのです。
もし担当役員がこのルールを知らなければ、みすみす大きなビジネスチャンスを逃すか、慌てて他の業者を探すことになっていたでしょう。
経営者がやるべきこと
この2つの事例から分かるように、金額計算のルールを正確に理解しているかどうかは、事業の安定に直結します。
ぜひ、貴社でも以下の2点を確認してみてください。
- 契約書や見積書を確認する
お客様支給の材料がある場合、その価格を把握し、合計額が許可基準を超えていないかチェックしましょう。 - 下請契約の内容を確認する
元請として工事を発注する際、下請契約の総額が特定建設業の基準に近づいていないか、常に意識しておきましょう。
これらの確認作業は、いわば会社の「健康診断」です。
うっかりポイントを早期に発見し、次の一手を打つための重要な経営判断と言えます。

専門家だからこそできる、一歩先のサポート
「ルールは分かったけど、自社で全部チェックするのは大変だ」
「判断に迷うグレーなケースが出てきた…」
「そろそろ特定建設業許可も視野に入れたいが、何から始めればいいか分からない」
そのような悩みをお持ちになるのは当然です。
行政書士は、単に書類を作成するだけが仕事ではありません。
コペル行政書士事務所では、お客様の事業内容や将来のビジョンを丁寧にお伺いした上で、
- 日々の契約における法的なリスク診断
- 許可の区分変更(一般→特定)や業種追加の最適なタイミングのご提案
- 複雑な申請書類の作成から、行政庁との折衝、許可取得までの一貫したサポート
など、あなたの会社の成長フェーズに合わせた、オーダーメイドのコンプライアンス体制構築をお手伝いします。
建設業界の法律は、頻繁に改正され、解釈も複雑です。
経営者の皆様が安心して本業に集中できるよう、面倒で専門的な手続きは、私たち専門家にお任せください。
まずは、あなたの会社の現状や、将来への想いをお聞かせください。
そこから、一緒に最適な道筋を探していきましょう。
初回のご相談は1時間無料です。下記よりお気軽にご連絡ください。


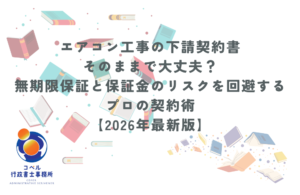
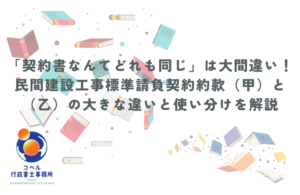
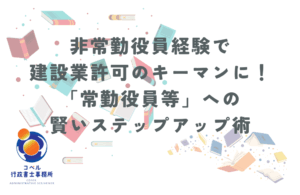




コメント