「うちは小さい工事しかやらないから、建設業許可は関係ないよ」
「500万円未満の工事なら、何も手続きはいらないんでしょ?」
こんにちは、佐世保市の行政書士の武藤です。
もしそう考えているなら、この記事を最後まで読んでください。その考えには、事業の存続を揺るがしかねない、大きな落とし穴が隠れているかもしれませんよ。
建設業界には、一見すると分かりにくいルールがたくさんあります。軽微な工事のみを受注する業者様は建設業許可が不要な認識が一般的ですが、思わぬところで法律違反となってしまうリスクが潜んでいるのです。
また、建設業許可をいよいよ取得する際に過去の工事実績(軽微な工事)が認められなかったら積み上げてきた期間が無駄になってしまいます。これだけは避けたいですね。
この記事では、忙しい事業主の方でもスラスラ読めるように、「つまり、どういうこと?」「じゃあ、何をすればいいの?」という視点で、軽微な工事の基本から、特に注意が必要な専門工事の登録制度まで、徹底的に解説していきます。
自社の状況が気になった方は以下からお問い合わせ可能です。

- 一人親方や小規模な工務店を経営している事業主の方
- リフォーム、内装、塗装など、比較的小規模な工事を専門に請け負っている方
- 「500万円未満なら許可不要」という知識しか知らない方
- 元請けとして、下請け業者に仕事を依頼する立場にある方
- これから建設業で独立・起業を考えている方
建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。
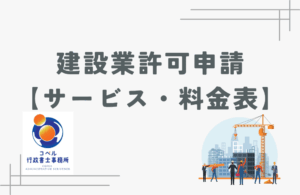
その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

- 建設業許可が不要な「軽微な工事」の正確な金額基準
- 請負金額を計算するときの「見えないコスト」の正体
- 軽微な工事でも別途手続きが必要になる3つの専門工事(解体・浄化槽・電気)の具体的な内容
- 各専門工事で必要になる登録・届出の具体的な手続きと要件
- 「会社の場所」と「現場の場所」が違う場合の注意点
- 法令違反をするとどうなるか、そのリアルなリスク
最後まで読めない!という方へ【この記事の3行まとめ】
- 500万円未満の工事でも、消費税や材料費、運送賃を含めて計算する必要があるため、気づかぬうちに超過している可能性がある。
- 「解体」「浄化槽」「電気」の3つの工事は、金額に関わらず、建設業許可とは別の「登録」や「届出」が法律で義務付けられている。
- 解体と浄化槽工事業登録の届出は、実際に工事を行う都道府県ごとに必要で、自社の場所とは関係ないので要注意。
工事実績の蓄積以外にも常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)や営業所技術者の要件を備えることも重要です。
以下の記事で詳しく解説しています。


細かい話ですが、初めて建設業許可が必要になるタイミング(軽微な工事段階)と特定建設業許可の取得を検討する際では契約金額の数え方が違います。ぜひ一緒にご確認ください。

「軽微な工事」の基本と3つの落とし穴
まずは基本の確認から始めましょう。「軽微な工事」とは、建設業法で「これくらいの規模の工事だけを請け負うなら、建設業許可はなくてもいいですよ」と定められている工事のことです。500万円未満の工事(建築一式工事は1500万円未満)が該当します。
しかし、この「くらい」がクセモノ。多くの人が勘違いしやすいポイントが3つあります。
「軽微な工事」の金額基準
工事の種類によって、2つの基準があります。
| 工事の種類 | 金額の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 (総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。新築や大規模な増改築など) | ①1件の請負代金が1,500万円未満(税込) または ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の半分以上を居住用として利用) |
| 建築一式工事以外の専門工事 (大工、内装、塗装、左官、電気、管など27種類の専門工事) | 1件の請負代金が500万円未満(税込) |
多くの中小事業主の方に関係するのは、下の「専門工事」でしょう。「うちは500万円未満だから大丈夫」と安心する前に、次の3つの落とし穴をチェックしてください。
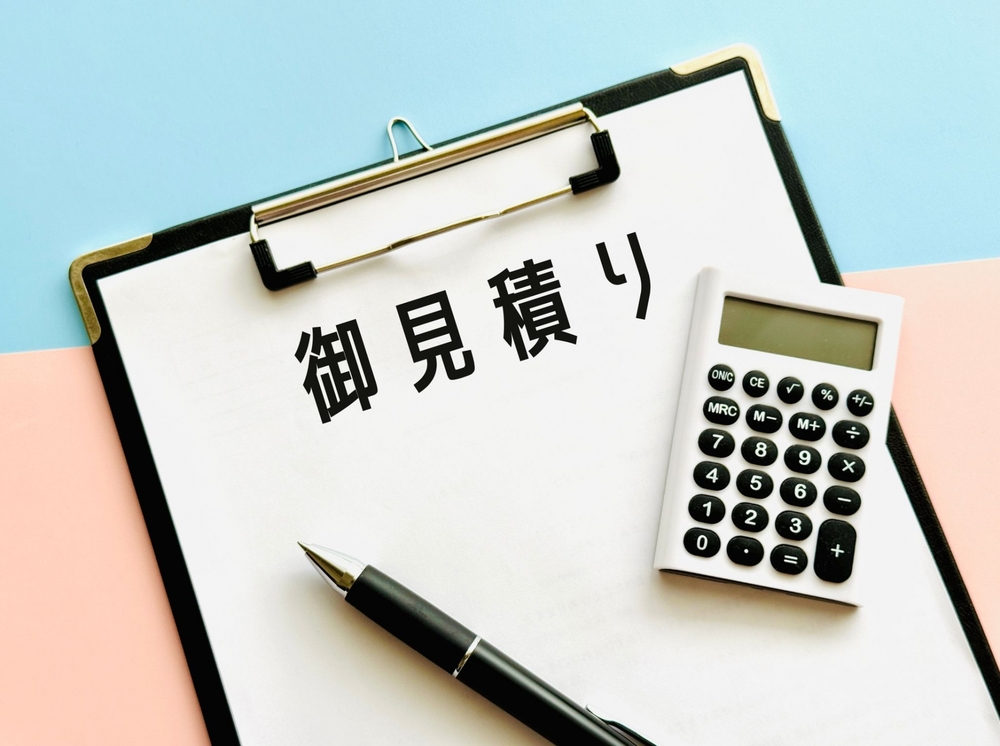
落とし穴①:消費税を忘れていませんか?
「500万円未満」という基準は、税抜ではなく消費税込みの金額で判断されます。
【具体例】
- 見積書の金額:480万円(税抜)
- 消費税10%を加えると… 528万円(税込)
この場合、税抜では500万円未満ですが、税込では500万円を超えてしまいます。したがって、この工事は「軽微な工事」には該当せず、建設業許可が必要になります。見積もりを出す際は、必ず税込価格で判断する癖をつけましょう。
落とし穴②:お客様が支給した材料費や運送賃、計算に入っていますか?
お客様(注文者)から「エアコン本体はこちらで用意します」「キッチンシステムは支給します」といった形で材料の提供を受けるケースは少なくありません。この場合、その材料の市場価格も請負代金に含めて計算しなければなりません。
【具体例】
- あなたの工事請負代金:400万円
- お客様が支給した高級システムキッチンの市場価格:150万円
- 合算した請負代金の額:550万円
これも500万円を超えてしまうため、建設業許可が必要です。「工事費としてもらうお金だけ」で計算すると、知らないうちに法律違反を犯すことになります。
落とし穴③:契約を分けてもダメです!
「900万円の工事だけど、450万円の契約2本に分ければ大丈夫だろう」…実これ通用しません。
弊所も以前、ご相談をいただいたことがあるので、みなさん気になるところかなと思います。
正当な理由なく工事を分割して契約しても、各契約の請負代金を合計した額で判断されます。行政は契約書の形式だけでなく、工事の実態を見ています。工期や工事場所が同じであれば、一つの工事と見なされ、合算されてしまいます。
許可不要でも「待った!」がかかる3つの専門工事
さて、第1章の落とし穴をクリアし、請負金額が500万円未満に収まったとします。「これで安心!」と思うのは、まだ早いのです。
一部の専門工事は、その工事が持つ危険性や環境への影響から、建設業法とは別の法律で特別なルールが定められています。つまり、たとえ10万円の工事であっても、以下の3つの工事を行う場合は、別の手続きが必要になるのです。
①解体工事
例)「店舗の内装をリフォームするので、古い壁や床を全部撤去してほしい。工事費は80万円くらいだよ」
この場合、金額は500万円未満なので建設業許可は不要。しかし、建物の構造部分などを取り壊す「解体工事」を行うには、『建設リサイクル法』に基づく「解体工事業登録」が必須です。
建物を解体する際は、アスベストなどの有害物質が飛散したり、廃材が不適切に処理されたりするのを防ぐため、専門知識を持つ業者しか行ってはいけないというルールです。その証明書が「解体工事業登録」なのです。
取るべきアクション
- 技術管理者を用意する:解体工事の8年以上の実務経験者や、特定の資格を持つ人を「技術管理者」として営業所ごとに置く必要があります。
- 工事を行う都道府県で登録する:会社の場所ではなく、実際に解体工事を行う場所の都道府県庁の窓口で登録申請をします。
※例外:建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている場合は、この登録は不要です。すでに解体工事を行うことができると建設業許可により認められているため。

②浄化槽工事
例)「下水道が通ってない地域で家を建てるので、浄化槽の設置をお願いしたい。費用は100万円ほどです
これも金額的には軽微な工事ですが、浄化槽の設置や修理を行うには、『浄化槽法』に基づく「浄化槽工事業者登録」(または届出)が必要です。
浄化槽は、家庭から出る汚水をきれいにして川に流すための重要な設備です。設置に不備があると、環境汚染に直結してしまいます。そのため、専門の資格を持った技術者がいる業者でなければ工事ができないルールになっています。
取るべきアクション
- 浄化槽設備士を配置する:国家資格である「浄化槽設備士」を営業所ごとに置く必要があります。
- 工事を行う都道府県で登録・届出をする:これも解体工事と同じく、実際に浄化槽工事を行う場所の都道府県に登録申請が必要です。
※例外:建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかを持っている場合は、登録より簡単な「特例浄化槽工事業者」の届出で済みます。解体業のケースと同く、許可により業務の遂行能力が担保されているためです。
③電気工事
例)「リフォームに合わせて、コンセントの増設や照明器具の取り付けをしてほしい」
軽微な電気工事であっても、電気を扱う工事を事業として行うには、『電気工事業法』に基づく「電気工事業者登録」(または届出)が原則として必要です。
電気工事は、一歩間違えれば火災や感電事故につながる非常に危険な作業です。そのため、資格を持った人が責任者となり、適切な器具を備えた業者でなければ、事業として電気工事を行ってはいけないと厳しく定められています。
取るべきアクション
- 主任電気工事士を配置する:第一種電気工事士、または3年以上の実務経験がある第二種電気工事士を「主任電気工事士」として営業所ごとに置く必要があります。
- 営業所のある都道府県で登録・届出をする:電気工事の場合は解体工事、浄化槽工事と少しルールが異なり、営業所の所在地を管轄する都道府県に登録・届出を行います。複数県に登録をする場合は、産業保安監督部長か経済産業大臣あてに提出をします。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
※例外:建設業許可(業種は問わない)を持っている場合は、登録より簡単な「みなし登録電気工事業者」の届出で済みます。理由は既出の二つと同じです。
「ウチは長崎だけど、現場は熊本」営業所と現場が複数県になる場合
多くの事業主の方が混乱するのが、この「管轄」の問題です。
解体工事と浄化槽工事は、『工事現場主義』です。
つまり、あなたの会社が長崎県にあっても、熊本県で解体工事や浄化槽工事を行うのであれば、熊本県知事に対して登録が必要になります。
一方で、電気工事は『営業所主義』です。
佐賀県にしか営業所がない会社であれば、福岡県や長崎県で電気工事を行う場合でも、佐賀県知事への登録・届出だけでOKです。
この違いは非常に重要なので、自社がどのエリアでどんな工事をするのかを正確に把握しておく必要があります。

まとめ:法令遵守は、あなたの事業と従業員を守る最大の防御策です
「面倒だな」「バレなきゃいいか」…そう思う気持ちも分かります。しかし、無許可や無登録での営業が発覚した場合のリスクは、あなたが想像するよりもずっと大きいものです。
- 罰金や懲役などの刑事罰
- 行政からの営業停止命令
- 公共工事の指名停止
- 元請けからの取引停止
- 社会的信用の失墜
たった一度のルール違反が、積み上げてきた信頼と実績をすべて失うことにつながりかねません。そんなのあまりにもったいないですよね。法令を正しく理解し、遵守することは、面倒な手続きではなく、あなたの会社と従業員、そしてお客様を守るための最も重要な経営判断なのです。
「自分の場合はどうなるんだろう?」
「必要な手続きが複雑でよく分からない…」
「技術者の要件を満たしているか不安だ」
「絶賛、許可取得の要件を積み上げている最中で、いずれは建設業許可をとりたい!」
少しでもそう感じたら、専門家の力を借りるのが一番の近道です。複雑な法律の解釈や、面倒な書類の準備や作成、行政庁とのやり取りはプロに任せて、安心して本業に集中してください。
当事務所では、建設業を営む事業主の皆様を全力でサポートするため、初回1時間の無料相談を実施しております。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。
問い合わせフォームや公式LINEからは24時間お問い合わせが可能です。事業を守るための第一歩として、ぜひお気軽にご連絡ください。


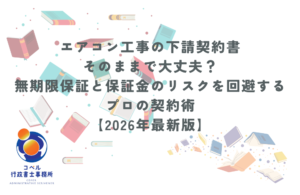
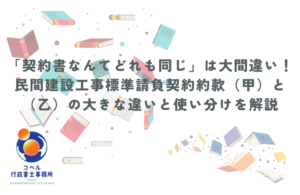
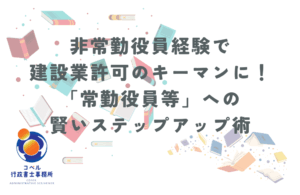



コメント