「長年続けてきた建設業、そろそろ次の世代にバトンタッチしたいけど、建設業許可ってどうなるの?」
「息子に事業を譲りたいけど、許可を取り直すのは大変そう…」
建設業を営む社長様、親方様、こんなお悩みはありませんか?建設業界では、経営者の高齢化や後継者不足が課題となっています。大切に育ててこられた事業を、スムーズに次世代へ引き継ぐことは、多くの建設業者様にとって喫緊のテーマでしょう。
以前は、事業を譲り渡す場合、元の許可は廃業し、新しい事業主が改めて許可を取り直す必要がありました。これでは、許可が下りるまでの間、工事が請け負えない「空白期間」が生まれてしまい、事業の継続性や取引先との関係に影響が出かねませんでした。
しかし、ご安心ください!平成2年(2020年)10月1日に施行された改正建設業法で、この問題点を解消する新しい道が開かれました。それが、建設業法第17条の2に定められた「事業譲渡等に係る認可制度」です。この制度を活用すれば、一定の条件を満たすことで、建設業許可を空白期間なく、次の世代へ引き継ぐことが可能になったのです。
この記事では、特に「許可を持つ個人事業主のお父様・お母様から、まだ許可を持っていない息子・娘さんへ」といった個人間の事業承継を念頭に、この認可制度の基本から具体的な手続き、クリアすべき要件まで、初心者の方にも分かりやすく、順を追って徹底解説していきます。専門用語も都度かみ砕いて説明しますので、じっくりお読みいただき、未来への大切な一歩を踏み出すためのお力になれば幸いです。
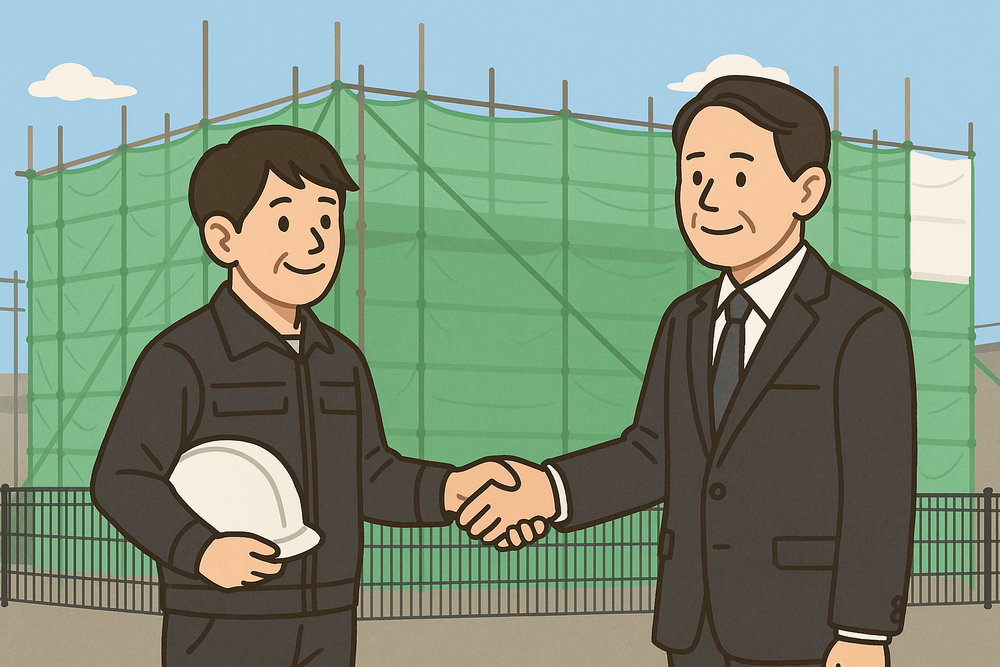
・建設業の個人事業主の親御さん
・特に「息子、娘に事業を継がせたいけど、手続きが難しそうで不安」な方
・もしくは、「すでに事業承継を進めてるが許可手続きを知らない」方
・「建設業許可ってそもそも何?」という基礎
・「旧制度の面倒さと、新制度でどう楽になったか」という構造の変化
・「17条の2って実際どう使うの?」という実務の流れ
そもそも建設業許可って何?~基本の「き」~
建設業者様向けのサービス内容に関しては以下をご覧ください。
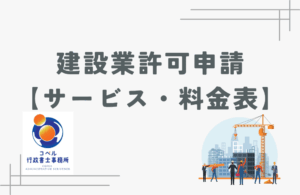
その他のサービス内容に関しては以下をご覧ください。

まず、建設業許可制度の基本をおさらいしましょう。「うちはずっと許可取ってやってるから今更…」と思われるかもしれませんが、承継する側(譲受人)にとっては、ここがスタート地点です。
なぜ許可が必要なの?
建設工事は、その適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することが求められています(建設業法第1条)。そのため、一定規模以上の建設工事を請け負うには、原則として建設業の許可が必要とされています(建設業法第3条)。「軽微な工事」を除き、無許可で工事を請け負うことは法律で禁止されています。
許可の種類って?
建設業許可には、大きく分けて2つの区分と29の業種があります。
一般建設業と特定建設業:下請に出す工事の金額によって区分されます。元請として受注した1件の工事について、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は「特定建設業」の許可が、それ以外の場合は「一般建設業」の許可が必要です。
29の業種:土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事…といったように、専門工事ごとに許可が分かれています。
事業承継の際には、譲渡人が持っている許可業種を、譲受人が引き続き営むために引き継ぐことになります。
誰が許可を出すの?
建設業許可は、営業所の所在地によって、国土交通大臣または都道府県知事が許可を出します。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合:国土交通大臣許可
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合:都道府県知事許可
この記事では、主に都道府県知事許可のケースを想定して解説を進めます。
事業承継のカタチ~どんな方法で引き継げる?~
建設業の事業承継には、いくつかの方法があります。
- ①事業譲渡
-
会社(法人)や個人事業主が営んでいる事業の全部または一部を、他の会社や個人に譲り渡すことです。今回のメインテーマである「個人事業主のお父さんから息子さんへ」というケースも、この事業譲渡に該当します。1 譲り渡す人を「譲渡人」、譲り受ける人を「譲受人」と呼びます
- ②合併
-
複数の会社が一つになることです。例えば、A社とB社が合併して新しいC社になる(新設合併)、またはA社がB社を吸収する(吸収合併)といった形があります。
- ③会社分割
-
会社が営む事業の一部または全部を切り離して、別の会社に承継させることです。
- ④相続
-
個人事業主である建設業者が亡くなった場合に、その相続人が事業を引き継ぐことです。
令和2年の法改正では、これらの事業譲渡、合併、会社分割、そして相続について、それぞれ許可を引き継ぐための認可制度が設けられました。 本記事では、この中でも特に「①事業譲渡」に焦点を当て、個人事業主間で許可を引き継ぐ場合の流れや要件を詳しく見ていきましょう。
昔は大変だった…事業承継の課題と「空白期間」という壁
新しい認可制度が導入される前は、建設業の事業承継は簡単なことではありませんでした。
旧制度の大きな問題点:許可の取り直しが必須
以前の制度では、事業譲渡や合併などがあっても、建設業許可そのものを引き継ぐという概念がありませんでした。
そのため、例えばお父さん(譲渡人)が事業をやめ、息子さん(譲受人)が事業を引き継ぐ場合、お父さんは建設業許可の廃業届を出し、息子さんは新たに建設業許可を申請し直さなければなりませんでした。
「空白期間」という悩ましい存在
この「許可の取り直し」には、大きな問題が伴いました。それは、「空白期間」の発生です。
廃業届を出してから、新しい許可が下りるまでの間は、当然ながら無許可の状態になります。この期間は、軽微な工事を除き、建設工事を請け負うことができませんでした。新しい許可が下りるまでには、申請書類の準備から審査完了まで数ヶ月かかることもあり、その間、事業がストップしてしまうリスクがあったのです。
この空白期間は、経営上の大きな不安材料でした

・進行中の工事はどうなるのか?
・新しい仕事を受注できない…
・従業員の雇用や給与は?
・取引先からの信用は大丈夫だろうか?
こうした課題を解決するために、建設業界からは長年、許可承継制度の創設が望まれていました。
ついに道が開かれた!改正建設業法と「認可制度」の登場
建設業者様の切実な声に応える形で、令和2年10月1日、改正建設業法が施行され、待望の建設業許可の承継制度がスタートしました。 この改正の目玉の一つが、建設業法第17条の2に規定された「事業譲渡等に係る認可制度」です。
建設業法第17条の2「事業譲渡等に係る認可」とは?
この条文を簡単に説明すると、「建設業者が、持っている建設業許可に係る建設業の全部を譲渡する場合、譲渡する人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)が、あらかじめその譲渡について行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の認可を受けたときは、譲受人は譲渡人の建設業者としての地位を承継する」というものです。
ポイントは以下の3つです。
- リ「建設業の全部」の譲渡であること:一部の業種だけを譲渡する場合は、この制度の対象外です。持っている許可業種すべてを譲り渡す必要があります。
- 「あらかじめ」認可を受けること:事業譲渡を実行する前に、行政庁から「OK」をもらう必要があります。これにより、譲渡と同時に許可が引き継がれるため、空白期間が生じません。
- 「認可」により「地位を承継」する:認可を受ければ、譲受人は、譲渡人が持っていた建設業許可業者としての立場をそのまま引き継ぐことができます。許可番号も原則として変わりません。
この認可制度の創設により、事業譲渡後もスムーズに事業を継続できるようになり、建設業者様にとって大きなメリットが生まれました。
ここが最大の関門!譲受人がクリアすべき「許可要件」とは?
事業承継の認可を受けるためには、事業を譲り受ける側(譲受人)が、新たに建設業許可を取得する場合と同様の許可要件を満たしている必要があります。これは非常に重要なポイントですので、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。主に建設業法第7条と第8条に定められています。
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等=経営業務の管理責任者)がいること(建設業法第7条第1号)
建設業の経営は、他の産業とは異なる特殊性があるため、適正な経営を行うためには一定の経営経験を持つ人が必要です。
事業主本人またはその支配人(商業登記された事業主の代理人)のうち一人が、以下のいずれかに該当する必要があります。
- イ:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主本人など)としての経験を有すること。
- ロ:国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。(例えば、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者経験がある場合など、細かい規定があります)
個人間の事業承継で、息子さん、娘さん(譲受人)に経営経験がない場合、この要件を満たすのが難しいことがあります。その場合は、お父様、お母様(譲渡人)が引き続き支配人として必要年数残り、経営をサポートするといった方法も考えられます。
経管要件に関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

2. 営業所ごとに営業所技術者(=専任技術者)を置いていること(建設業法第7条第2号)
建設工事の適正な施工を確保するためには、各営業所に一定の資格や実務経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。
以下のいずれかに該当する人が必要です。
- 国家資格者等:許可を受けたい業種に応じた国家資格(例:1級建築士、1級土木施工管理技士など)を持っている人。
- 実務経験者:
- 許可を受けたい業種に関して、大学の指定学科を卒業後3年以上、または高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験がある人。
- 学歴に関わらず、許可を受けたい業種に関して10年以上の実務経験がある人。
- 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人。
この営業所技術者は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事している必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

3. 誠実性があること(建設業法第7条第3号)
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。例えば、過去に法律違反を犯して罰則を受けたり、営業停止命令を受けたりしていないかなどが問われます。
財産的基礎または金銭的信用があること(建設業法第7条第4号)
建設工事を請け負うためには、資材の購入や労働者の確保など、一定の資金力が必要です。
- 一般建設業の場合:以下のいずれかを満たす必要があります。
➡自己資本の額が500万円以上であること。500万円以上の資金を調達する能力を有すること(金融機関の預金残高証明書などで証明)。
欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)
たとえ上記の1~4の要件を満たしていても、以下の欠格要件に一つでも該当する場合は許可を受けることができません。代表的なものをいくつか挙げます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 不正な手段により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
- 営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建設業法や建築基準法、労働基準法などの一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員等であること、または暴力団員等がその事業活動を支配する者。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。
これらの許可要件は、譲受人(息子さん)がクリアしなければならないハードルです。お父さん(譲渡人)が長年培ってきた実績とは別に、息子さん自身がこれらの基準を満たす必要がありますので、事前の確認と準備が非常に大切です。
スムーズな引継ぎのためのその他のポイント
建設業許可の認可手続き以外にも、事業承継を円滑に進めるためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
- 事業譲渡契約の締結:いつ、何を、いくらで譲渡するのか、従業員や取引先との契約はどうするのかなど、事業譲渡の内容を明確にするために、譲渡人と譲受人の間で事業譲渡契約書をきちんと作成しましょう。
- 従業員の引継ぎ:従業員がいる場合は、その雇用契約をどう引き継ぐのか、処遇はどうなるのかなどを従業員によく説明し、合意を得ることが大切です。社会保険や労働保険の手続きも忘れずに行いましょう。
- 取引先への通知:これまでお世話になった発注者や協力会社、仕入先などには、事業承継を行う旨を事前に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。
- 税金のこと: 税金関係は複雑ですので、税理士さんなどの専門家に相談することをお勧めします

まとめ~計画的な準備で、大切な事業を未来へつなごう!~
建設業許可の事業承継は、かつての「許可取り直しによる空白期間」という大きな壁がありましたが、建設業法第17条の2の認可制度の登場により、その壁は取り払われました。事前にしっかりと準備し、行政庁の認可を受けることで、空白期間なくスムーズに許可と事業を引き継ぐことが可能になったのです。
この制度のメリットを最大限に活かすためには、何よりも計画的な準備が不可欠です。
- 譲受人(後継者)が許可要件をクリアできるか、早めに確認しましょう。特に経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は、一朝一夕に満たせるものではありません。
- 手続きには時間がかかります。承継したい時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
- 不明な点や不安なことは、抱え込まずに専門家や行政庁に相談しましょう。
建設業者様へ:未来へのバトンタッチ、今こそ準備を始めませんか?
建設業許可の承継って、調べれば調べるほどややこしくて不安になるものだと思います。でも、きちんと準備すれば、許可を引き継いで安心して次の世代にバトンを渡すことは可能です。
コペル行政書士事務所は建設業・産廃業に関する申請に特化した行政書士事務所です。不安なまま進めるより、一度話してみませんか?状況を聞いたうえで、できるだけわかりやすく、実現できる方法を一緒に考えましょう!
初回1時間相談無料です!下記ボタンよりお気軽にお問い合わせください(^-^)
対応地域と取扱サービスは下記ページよりご確認ください。
サービス一覧以外でも対応可能ですので、まずはご相談ください。

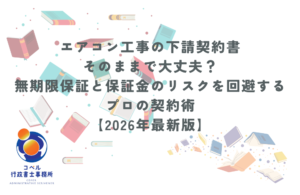
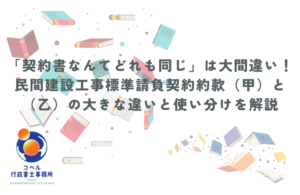
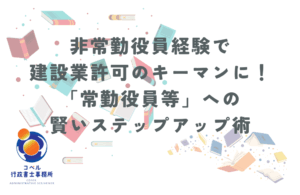





コメント